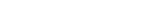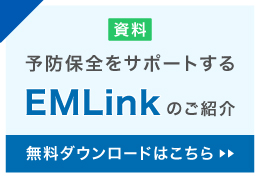予防保全とは|予知保全・事後保全との違いやメリット、導入時のポイントについても解説
作成日: 更新日:

※こちらの記事にはPRを含みます
この記事でわかること
日本の基幹産業である、石油化学や化学プラントなどのプロセス産業は
設備の老朽化や技術者不足、資材や人件費の高騰などといった多くの課題に直面しており、
人材獲得やコスト削減、業務効率化、既存資産の有効活用などが急務となっています。
これらの課題に対する有効なアプローチの一つが「予防保全」です。
本記事では、予防保全の基本的な考え方や、他の予知保全・事後保全との違い、
プロセス産業との関連性、導入のメリットやデメリット、実施する上での重要なポイントなどについて詳しく解説していきます。
予防保全とは?
「予防保全」とは、設備に故障の兆候が表れる前に、事前に計画したスケジュールに基づいて点検や部品の交換を実施する保全手法を意味します。これにより突発的なライン停止などのトラブルを未然に防ぐことができ、設備の長期的かつ安定した稼働を支援します。
特にプロセス産業など設備の停止が安全性や生産性などに大きく影響する現場は、この「予防保全」という考え方や手法が重視されます。
では、混同されがちな、「予知保全」や「事後保全」とはどのように違うのでしょうか?ここからは、他の保全方法との違いを詳しく見ていきましょう。
予防保全と予知保全の違い
「予防保全」とよく混同される保全手法として「予知保全」があります。
予防保全が、設備が壊れる前に一定の使用期間や稼働時間に点検や交換を行う保全手段であるのに対し、予知保全は設備の稼働状況やセンサー情報をリアルタイムで監視しながら、異常の兆候が見えたタイミングで対応する保全手法です。
予知保全ではモニタリングやAIによる将来の状況の予測モデルを活用し、「壊れそうな時にだけ」対応することを目指します。
予知保全は、過剰な保全作業を抑制しつつ、設備の状態をリアルタイムで把握することができるスマートで無駄のない保全方法ですが、センサーなどを設置して常時モニタリングが必要なため、導入コストや維持管理コストが高くなる傾向にあります。また異常を検知したタイミングでは、既に重大な故障が進行しているといったケースもあるため、その点にも注意が必要です。
予防保全と事後保全の違い
では、「予防保全」と「事後保全」の違いは何でしょうか?
事後保全は、設備が故障してから修理や交換を行うという古くから用いられてきた保全手法です。
シンプルで分かりやすい方法ではありますが、一度発生してしまうと生産ラインが停止したり品質不良につながるなど、重大な影響を招く恐れがあります。
ここで改めて「予防保全」「予知保全」「事後保全」3つの保全の違いをおさらいしてみましょう。
| 保全方式 | 概要 | タイミング | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 予防保全 | 計画に基づき点検や部品交換を実施 | 稼働状況や期間に基づくスケジュールで実施 | 計画的な対応・突発トラブルの回避・コストの予見性向上など | 過剰整備・タイミングの判断の難しさなど |
| 予知保全 | センサーやデータ解析を活用し、異常を検知して保全を実施 | 故障の兆候を検知したタイミングで実施 | 設備の寿命を最大化・過剰な保全を抑制 | 導入や維持コストが大きい・重大な故障が進行している可能性 |
| 事後保全 | 設備が故障してから修理や交換を実施 | 故障発生後に実施 | 初期コストや点検コストが不要・シンプルな運用 | 突発的な停止や品質不良のリスク |
予防保全とプロセス産業の維持発展との関係
日本の基幹産業である石油化学や化学プラントなどのプロセス産業において「予防保全」という方法が重視されてきた理由にも、これらの保全手法の特徴が深く関係しています。
プロセス産業は現在、設備の老朽化や技術者不足、資材や人件費の高騰などの課題に直面しています。こうした環境下で、人材獲得・育成やコスト削減、業務効率化、既存資産の有効活用が重要なテーマとなっています。
これらの課題を乗り越え、安定的かつ継続的な稼働を実現していくためには適切な保全が欠かせません。
しかし、生産設備は「多様な部品の複雑な集合体」であり一品一様(=工場ごとに異なった様式)な仕様の性質を持っています。加えて「固有の運転履歴・使用環境に基づく独特な特徴」を持っているために、老朽化や破損の形態及びリスクを一律に予測することは難しいのが現状です。
理想的には、それぞれの設備が「壊れる直前」に「壊れる箇所」を特定して、費用対効果に見合った保全対応を行うことで、故障などの不具合を事前に回避したり、そのインパクトを抑制し、設備のより長い継続運転を実現することが求められます。
その理想を現実的な形で落とし込んだものが「予防保全」です。
単なる定期点検や部品交換にとどまらず、設備のデータを収集しリスクとコストのバランスを踏まえた最適な対策を講じる保全戦略そのものが「予防保全」なのです。
予防保全の重要性と導入のメリット
改めて予防保全の重要性と導入した場合のメリットについて整理していきましょう。
設備の稼働率が生産性に直結する現場では、予防保全の導入が企業全体のパフォーマンス向上につながります。ここでは予防保全の重要性と導入による効果を整理します。
突発トラブルの回避
未然に点検や部品交換を行うことで突発的なトラブルのリスクを低減し、設備が安定稼働することにより、生産計画や納期遵守を実現できます。
製品の品質維持
劣化した設備での生産を続けると、商品の不良につながる恐れがあります。
コストの予見性向上
あらかじめ計画的に部品の交換や点検を行うため、修繕費が突発的に増加しにくく、予算計画が立てやすくなります。
劣化する前の対応が基本となるため、部品の劣化や設備の異常動作によって発生する事故などを未然に防ぐことができます。
予防保全は、メンテナンスは最小限になりリスクは避けられるが監視やモニタリングに大きな費用が掛かる予知保全、事前の費用は掛からないが、トラブルが発生した場合には大きなリスクにつながる事後保全と比較しても、コストとリスクのバランスが非常に良い方法であるといえます。
予防保全が財務諸表に及ぼす影響
意外と知られていませんが、予防保全は財務諸表に対しても貢献します。
例えば損益計算書に関するコスト削減という観点では、類似設備を含めた過去の事象や点検記録をもとに、設備群の最適な保全周期を算出することができます。ここからこれまで安全サイドに過剰投資しがちだった定期検査や工事の周期を現状のリスクを大きく損ねることなく、低減することも可能となります。また適切なタイミングでの設備投資を織り交ぜることで、老朽化の進行に伴う保全費用の加速度的な増加を抑えるという効果も期待できます。
更に、精緻な点検やリスク評価によって補修範囲を狭める検討ができる場合もあります。
また、貸借対照表に関するアセット最適化という観点からは、例えば設備ライフサイクルを踏まえた部品や予備品、資材の需要予測を精緻に行うことで、余剰在庫の削減を図ることも可能です。
設備投資が大きいプロセス産業においては、余剰資材在庫の回避によるキャッシュポジションの改善や廃棄損リスクの低減がこれまでも大きなテーマではありましたが、予防保全を実施することは、これらの改善の強力な一手としても期待されています。
予防保全における4つの観点
予防保全を効果的に実施するために、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
ここでは、予防保全を実施するうえで重要な4つのポイントについて解説していきましょう。
①データ収集基盤
予防保全における、はじめの重要な観点は、保全データという工程・設備・部署・使用目的ごとに様々なフォーマットで存在しうる情報を一定の枠に当てはめて収集していくため基盤づくりを行うことです。
どのような情報をどのように記録・管理していくのか、共通の枠組み作りを行うことことで、データの収集や分析が可能となります。
②継続的なデータ収集
次に重要なのが、現場での制御・監視技術(OT:Operational Technology)の活用や点検記録・不具合報告のオペレーションの効果的な運用により、この基盤をベースとして必要なデータを継続的に収集していく仕組みを構築することです。
長期間に渡る安定したデータの蓄積が、その後の分析や予測につながっていきます。
③収集データを価値あるデータへ
収集されたデータを単なる記録として終わらせることなく、情報技術(IT :Information Technology)の観点から、適切にリンクをさせ「価値あるデータ」へと昇華させていくプロセスも重要です。
点検の履歴や計測したデータを連携させ、傾向などを可視化することで、予測精度の向上につなげることが可能です。
④予測する仕組みづくり
最後に、これらの3つの仕組みを踏まえた上で、過去の経験則や機械設備の原理原則を前提とした「予測する」仕組みづくりを行うことが重要です。
この予測モデルを活用することで、将来的なトラブルを察知し、適切なタイミングでの判断材料を提供することが可能になるのです。
予防保全を適切に実施していくためには、この4つのポイントを押さえ、それぞれの仕組みを着実に構築・運用していくことが必要です。
予防保全のデメリットは?
これまでご紹介してきた通り、予防保全には多くのメリットがある一方で、いくつかの課題や限界もあります。
導入を検討する際には、デメリットも理解したうえで適切な方法を選択することが重要です。
予防保全を導入するデメリットについて、いくつか解説をしていきます。
過剰整備のリスク
「念のため交換」といった対応を重ねると、まだ使える部品を早期に交換してしまうムダも発生します。
タイミングの判断が難しい
一律でルールを定めたとしても、実際には機器ごとに劣化スピードや状況が異なるため、結果的に適切なタイミングではないケースが発生します。
記録や計画の工数がかかる
予防保全を実施するには、設備ごとの保全の履歴やスケジュールなどを管理、記録し続ける必要があります。特に人が不足している現場では、その管理や調整だけでも大きな負担となる場合もあります。
それぞれの保全方法のメリットデメリットを理解しながら、適切な方法を選択していくことが重要といえるでしょう。
適切な予防保全を実現するために
予防保全を適切な形で実現していくためには、前述の「データ基盤の構築」「継続的なデータ収集」「価値あるデータへの変換」「予測モデルの構築」といったポイントを押さえ、バランスよく実施していくことが求められます。
しかしながら実際には、測定対象・事象が状況によって時々刻々と変わり、現場では極めてファジーな情報が入り乱れるため判断が難しいケースも多くあります。そのため機械的に完全自動化されたシステムよりも、人が目で見て考える仕組みの方が効果・効率の両面でより優れたシステムとなるケースも多いのが現実です。
だからこそ人と技術を上手く組み合わせ、仕組み化して回す活動の確立(「人中心の予防保全」)が重要なのです。
とはいえ、限られた人員や予算の中で最適な仕組みを構築するのは難しく、悩まれる方も多いのではないでしょうか。
そんな現場の声に応えるのが、「EMLink」 というアプリケーションです。
予防保全をサポートする EMLink
ここまでご説明してきた通り、予防保全はリスクとコストのバランスに優れた有効な保全手法です。
しかしながら、実際の仕組み構築はとても難しく、またすべてを自動化・システム化しようとすると莫大な費用や時間が必要で、どこから手を付けるべきか迷われる方も多いのではないでしょうか。
この仕組み構築をシンプルかつ迅速にサポートするのが「EMLink」というサービスです。
「EMLink」は保全に関する情報の一元可視化や業務の効率化、技術継承を実現しながら、保全コストの削減なども図ることが出来ます。
詳しい内容は資料をダウンロードしてご確認ください。
掲載内容
■ EMLinkの概要 ~プラント・工場の設備管理クラウド~
■ 設備保存における課題
■ EMLinkで実現できること
■ EMLinkの主要機能
■ EMLinkのデータ構造イメージ
■ EMLinkの活用シナリオ例
■ EMLinkの料金プラン
■ データ移行「丸ごと」お任せプラン
■ EMLinkが目指すデータ連携 ~製造現場のプラットフォーム型ERP~
※こちらは協力会社より提供の資料となります。さらに詳しい内容のご確認やご相談は直接やりとりいただく形となりますので、あらかじめご了承ください。